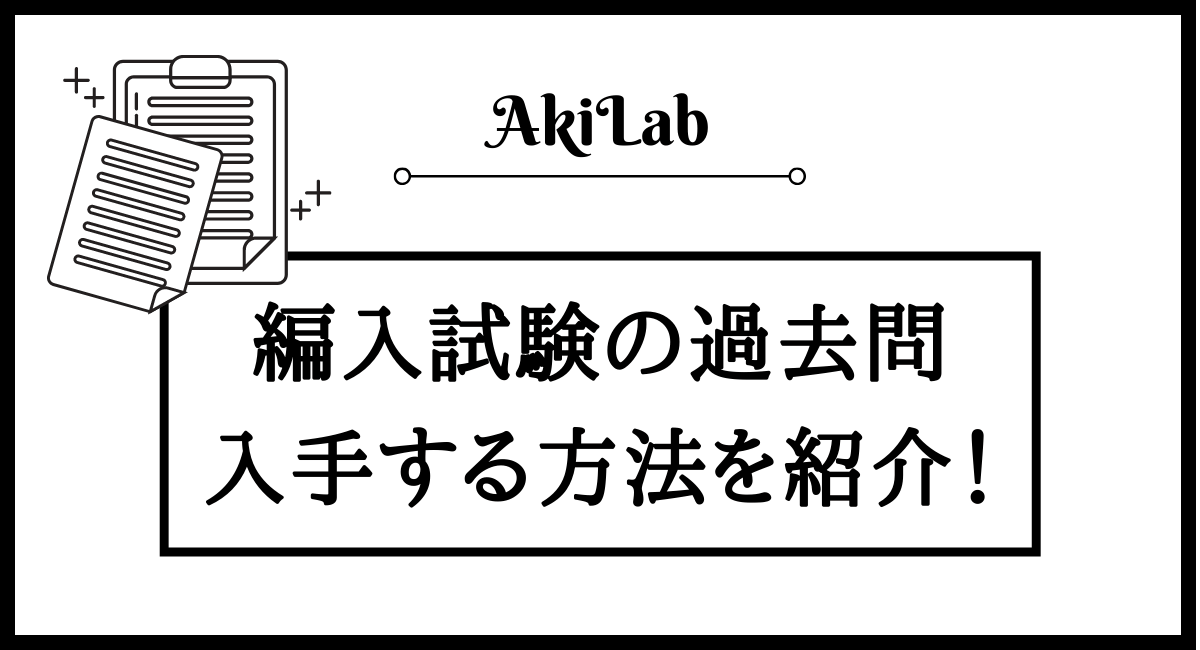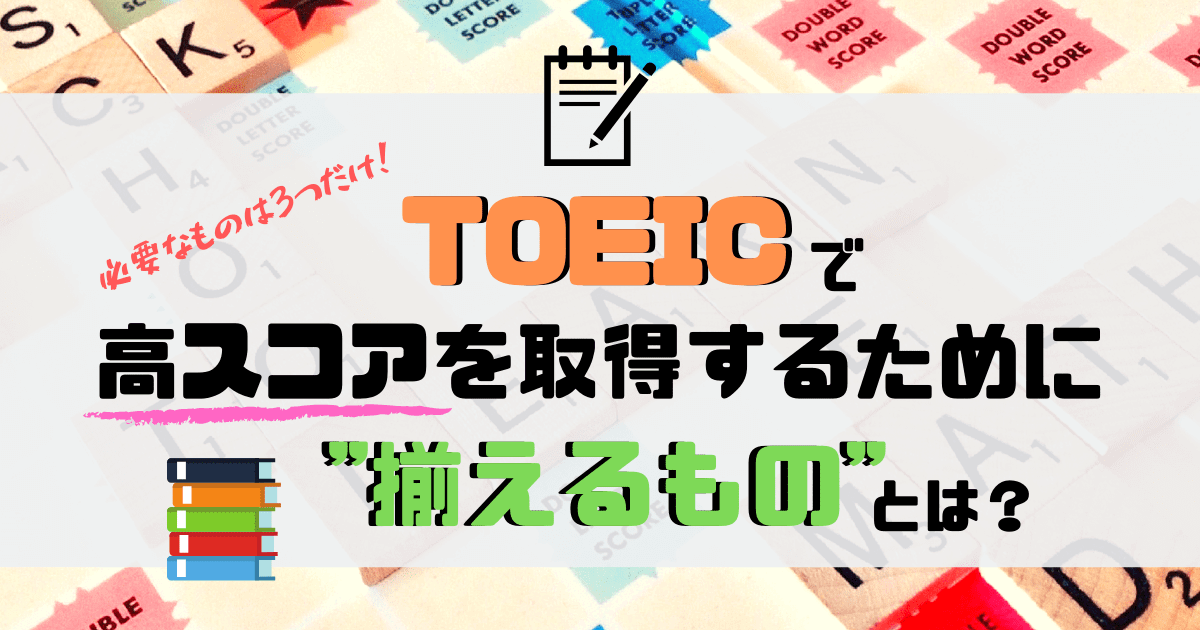TOEFLも大学編入に活用することができます!
どうも、専門学校から早稲田大学に3年次編入した経験を持ちます、アキラです。
皆さんは、「大学編入」を成功させるために英語の資格試験の勉強が必要になることをご存知ですよね。
この英語の資格試験とは、例えば「TOEIC」や「英検」のことを指しています。
大学編入において、特に重要性の比重が大きいのが「TOEIC」です。
出願時の「足切り」として指定されたTOEICスコアの取得が必要になったり、TOEICスコアが「英語試験の得点」として換算されたりするためです。
また、TOEICの他に、英検も大学編入で活用することができます。
指定された「英検取得級」を取得することで出願が認められる大学もあります。
現在、大学編入という目標を達成するために、TOEICや英検の勉強を必死に取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、このTOEICや英検と同じように、「TOEFL」と呼ばれる英語の資格試験も編入試験に活用することができます。
そこで今回は、「大学編入とTOEFLの関係性」について解説していこうと思います。
- 「そもそもTOEFLってどういう試験?」
- 「自分の志望校ではTOEFLを活用できる?」
- 「自分はTOEFLを勉強しないといけない?」
など、「大学編入とTOEFLの関係性」について疑問に感じることがある人は、ぜひ当記事を参考にしてみてください。
目次
そもそもTOEFLってどういう試験?
「大学編入とTOEFLの関係性」について話す前に、そもそも「TOEFL」とはどういう試験なのかについて少し触れていこうと思います。
TOEFLは「Test of English as a Foreign Language」の略で、「ETS」という団体によって開発された英語の資格試験です。
試験では、英語を「読む」「書く」「聞く」「話す」の4つの能力が測定されます。
大学入学レベルのテストは「TOEFL-iBTテスト」
一括りに「TOEFL」といってもいくつか種類がありますが、大学入学レベルのTOEFLとして広く利用されているのが「TOEFL-iBTテスト」です。
大学編入において提出が認められているTOEFLは、ほとんどがこの「TOEFL-iBT」となっています。
「TOEFL-iBT」の特徴は以下のようなかんじです↓
- テストセンターにて全セクションコンピュータ上で受験
- テスト所要時間は4-4.5時間(チェックイン・休憩含む)
※2019年8月1日以降はテスト時間が短縮されます。- 全セクションでメモをとること(Note-taking)が可能
- Speakingセクションでは、マイクに向かって話し、音声が録音される
- 同時に複数の技能を測定する問題(Integrated Task)が出題される
- スコアは点数に加え、「スコアの持つ意味」の解説 (Performance Descriptor)も示される
TOEFL-iBTは「テストセンター」と呼ばれるところで試験が行われ、すべての解答がコンピューター上で実施されます。
そしてテスト時間は「4-4.5時間」という長さ。
TOEIC(Listning & Reading)とは異なり、英語を「話す」テスト・「書く」テストも用意されています。
「読む」「書く」「聞く」「話す」のそれぞれのテストの時間・配点などをまとめると以下のようなかんじ↓
| セクション | スコア | スコアレベル |
|---|---|---|
| Reading 60~80分 |
0~30 | High(22~30) Intermediate(15~21) Low(0~14) |
| Listening 60~90分 |
0~30 | High(22~30) Intermediate(15~21) Low(0~14) |
| 休憩10分 | ||
| Speaking 20分 |
0~30 | Good(26~30) Fair(18~25) Limited(10~17) Weak(0~9) |
| Writing 50分 |
0~30 | Good(24~30) Fair(17~23) Limited(1~16)Score of zero(0) |
| Total | 0~120 | – |
TOEFLとTOEICの違い
TOEFL(TOEFL-iBT)とTOEIC(Listning & Reading)の「特徴的な違い」についてまとめてみます。
特徴的な違いとしては、以下のようなものが挙げられます↓
- 試験形式
- 試験時間
- 受験料
試験形式
TOEFLとTOEICは、その試験形式が大きく異なります。
TOEICは、リスニングパートとリーディングパートの二つに分けられていて、解答はマークシート方式となっています。
一方で、TOEFLは試験会場となる「テストセンター」にパソコンが用意されていて、そのパソコンを使って試験を進めていくことになります。
試験は「リスニング」「リーディング」の他に、「ライティング」「スピーキング」も用意されています。
「スピーキング(話す)」テストでは、頭に装着した「ヘッドセット」のマイクに向かって英語を話す「録音形式」となっている点も特徴的です。
試験時間
TOEFLとTOEICは「試験時間」が全くもって異なります。
TOEICの試験時間は、「リスニング:45分」「リーディング:75分」で実施されます。
計120分の試験時間ということですね。
一方でTOEFLは「4~4.5時間」の試験時間を要します。
受験料
TOEICの受験料は「7,810(税込)/1回」なのに対し、TOEFL-iBTの受験料は基本的に「US$245 /1回」となっています。
TOEFLは1回の受験料がものすごく高いことが分かりますね。
大学編入とTOEFLの関係性
ここからは、当記事のメインテーマでもある「大学編入とTOEFLの関係性」について解説していきます。
TOEFLスコアを提出できる大学・学部がある
大学編入を実施している大学の中には、出願時に英語の資格試験を提出させるところがあります。
その主な目的が「足切りライン」を設定するためです。
例えばTOEICなら、出願資格を「TOEIC600点以上」と設定しておくことで、事前に”それなりに英語の能力がある学生”が集まるようにしています。
この場合、TOEIC600点以上取得することができていない人は、編入試験に出願することすらできません。
基本的に足切りラインの設定はTOEICスコアを利用する大学が多いですが、TOEICの他に「TOEFLスコアの提出でもOK」という大学・学部も存在します。
例として、「名古屋大学 経済学部」の募集要項を確認してみましょう↓
【2】出願要件
TOEICまたはTOEFLを2016年10月4日以降に受験し、次の得点を取得していること。
- TOEIC:590点以上
- TOEFL-PBT:500点以上
- TOEFL-iBT:61点以上
- TOEFL-CBT:173点以上
名古屋大学経済学部では、出願時に「TOEICスコア」もしくは「TOEFLスコア」を提出させることで、足切りラインを設定していることが分かります。
このように、大学によっては「TOEIC」や「英検」以外に、「TOEFLスコア」の提出も可能なところがあります。
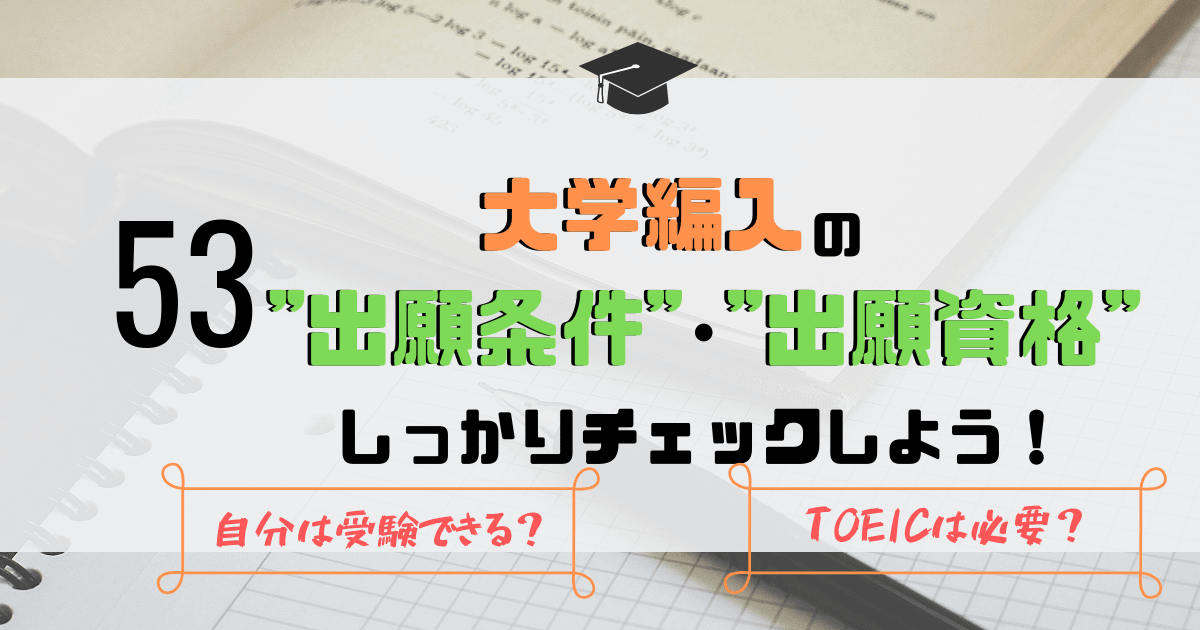 大学編入の出願条件・出願資格は早めのチェックが必要!
大学編入の出願条件・出願資格は早めのチェックが必要!
必ずTOEFLが必要な大学がある
大学編入を実施している大学・学部の中には、「必ず」TOEFLスコアを取得しなければいけないところもあります。
このような大学の編入試験に挑戦するためには、TOEFLの受験が「必須」となります。
出願時に「必ず」TOEFLを提出しなければいけない大学には、以下のようなところがあります↓
(一部例)
- 京都大学(法学部,経済学部,工学部)
- 神戸大学(国際人間科学部)
- 国際教養大学
- 神田外語大学(英米語学科)
- 明海大学(ホスピタリティツーリズム学部 ホスピタリティ・マネジメントメジャー)
- 国際基督教大学(教養学部 2年次)
- 法政大学(経営学部)
上記の大学の編入試験に挑戦したい人は、あらかじめTOEFL(基本はTOEFL-iBT)の対策をして、高いスコアを取得しておかなければいけません。
ちなみに、上記大学のうち、「国際教養大学」「神田外語大学」「明海大学」「国際基督教大学」はTOEFLスコアが指定されており、それぞれ
- 国際教養大学…(2年次編入)71 / (3年次編入)79
- 神田外語大学…79
- 明海大学…80
- 国際基督教大学…79
となっています。
(すべてTOEFL-iBTのスコア / 2022年度募集要項からの情報)
大学編入のためにTOEFLを勉強するのは「得策」か?
先述したように、大学編入を実施している大学によっては、出願資格として「TOEFLスコアの提出」も認めているところがあったり、「TOEFLスコアを”必ず”提出しなければならない」大学もあります。
それでは、大学編入を目指す編入受験生は「TOEFLの勉強」をすべきなのでしょうか?
実際に編入試験を経験し、早稲田大学をはじめ4つの大学に同時合格することができたボクの考えをまとめておきます。
「TOEFLスコアの提出が必須の大学」に挑戦する人は勉強しないといけない
まず当たり前のことですが、志望校が「TOEFLスコアの提出が必須」の大学である場合、必ずTOEFLの勉強をしなければいけませんね。
「TOEFLを提出してください」と言われているのに、特に何の対策もせずに、何となくTOEFLを受験しているようでは、編入試験に合格できるはずがありません。
上記で挙げた
(一部例)
- 京都大学(法学部,経済学部,工学部)
- 神戸大学(国際人間科学部)
- 国際教養大学
- 神田外語大学(英米語学科)
- 明海大学(ホスピタリティツーリズム学部 ホスピタリティ・マネジメントメジャー)
- 国際基督教大学(教養学部 2年次)
- 法政大学(経営学部)
の編入試験に挑戦を考えている方は、しっかりTOEFL対策を行いましょう。
この場合、勉強する英語の資格試験はTOEFLのみでOKです。
TOEFLの勉強に全集中力を注いでください。
「TOEFL以外でもOKな大学」なら勉強しない方が良い
自分が受験する大学では「TOEFL以外の資格試験(TOEICや英検)の提出が認められている」という方や、そもそも「出願資格として英語の資格試験の提出が求められていない」という方は、無理にTOEFLの勉強をしなくても良いです。
というか、個人的にはTOEFLの勉強は”しない方が良い”と思います。
TOEFLの対策に時間を費やすなら、TOEICの勉強をした方が「圧倒的にメリットが多い」からです。
ボクがそう考える理由は、TOEFLという試験はTOEICと比べて…
- 試験内容がハード
- 1回の受験料が高い
- (編入試験において)TOEICの方が汎用性が高い
からです。
TOEFLはTOEICと比べて「試験内容がハード」
上記で解説しているように、TOEFL(TOEFL-iBT)の試験では「Reading」「Listening」「Speaking」「Writing」のすべてをこなさなければいけません。
TOEIC(Listning & Reading)の試験内容は「Listening」と「Reading」のみなので、TOEFLがいかにハードな試験かが分かります。
試験時間もTOEICが「計120分」なのに対してTOEFLが「4~4.5時間」です。
こんなに長い時間も集中力が続くわけがないですし、1回のテストでベストパフォーマンスを発揮できるか想像してみても、微妙ですよね。
大学編入で合格を掴むためには、英語の資格試験の勉強以外に、「専門科目」の勉強もしなければいけません。
つまり、英語の資格試験の勉強に費やせる時間は限られているということです。
そんな中で、「Reading」「Listening」「Speaking」「Writing」それぞれの勉強に手をつけるのは非常に大変ですよね。
編入生にとっては、できるだけ勉強に向ける労力を抑えることができる「TOEIC」に挑戦した方がメリットが大きいです。
TOEFLはTOEICと比べて「1回の受験料が高い」
TOEFLはTOEICに比べて「1回の受験料が高い」という特徴があります。
「TOEFLテストの1回分の受験料=TOEICテストの5~6回分の受験料」となっています。
そのため、よっぽどお金に余裕がある人でない限り、1年に何度もTOEFLテストに挑戦するのは困難でしょう。
つまり、編入生がTOEFLに挑戦する場合、”少ないチャンス”の中で必ず良い結果を出さなければいけないのです。
これはなかなか厳しいですよね。
一方でTOEICなら良心的な受験料なので、「年に複数回」テストを受験することも可能です。
“数あるチャンス”の中から理想のスコアを1回でも叩き出せば良いので、TOEICを選んだ方が安心です。
TOEFLはTOEICと比べて「(編入試験において)TOEICの方が汎用性が高い」
編入試験においては、TOEICを「出願資格の証明として活用する」大学・学部が多いです。
つまり、「TOEICスコア」を取得できていれば、途中で志望校が変わったり、複数の大学を併願したりする場合でも、「出願資格を満たせない」という事態に陥るリスクは少なくなります。
TOEFLよりもTOEICの方が「汎用性が高い」のです。
このような理由から、「TOEFLテストの提出が必須」の大学が志望校でない限り、編入受験生は「TOEIC」の勉強をした方が良いと言えます!
 アキラ
アキラ
>> 就職に有利なTOEICスコアは?就活無双するための勉強法も解説
「大学編入とTOEFLの関係性」まとめ
今回は、「大学編入とTOEFLの関係性」についてまとめてきました。
- 大学編入に挑戦する編入受験生は「TOEFL」の勉強が必要?
- 編入試験でTOEFLが必要になる大学はどこがある?
- 自分はTOEIC・TOEFL・英検のどれを勉強すれば良い?
等の疑問を抱いていた方は、ぜひ当記事を参考にしてみてください。
もしあなたが「必ずTOEFLスコアの提出が必要になる大学」に挑戦しようとしている場合、専門科目の勉強と並行して、TOEFLも真剣に勉強しないといけないことを頭に入れておきましょう!