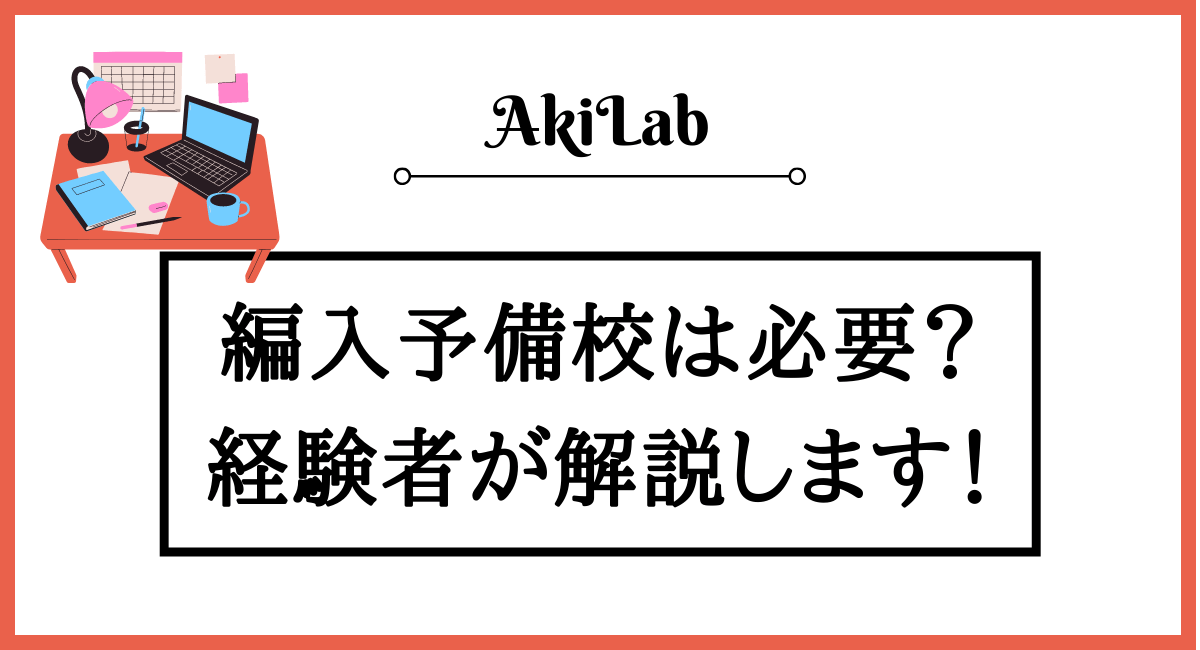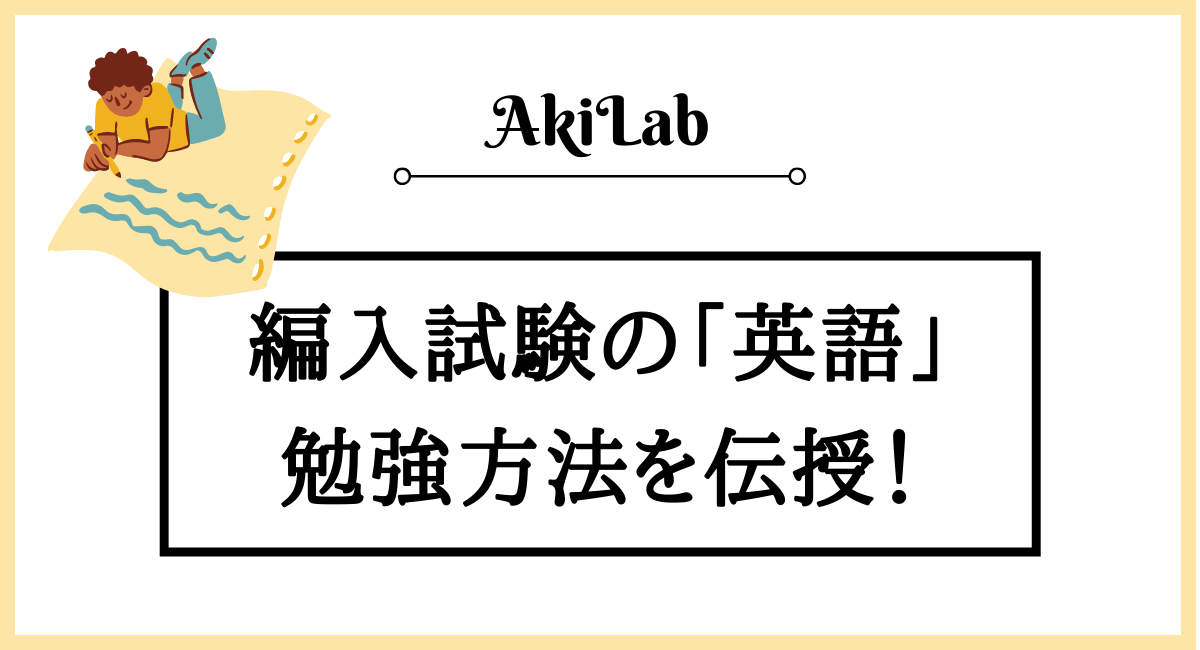大学編入の「滑り止め大学」について
解説していきます!
どうも、受験校5校のうち4校の編入試験に合格することができました、アキラです。
現在「大学編入」合格を目指して勉強を進めている編入受験生の中に、
大学編入の『滑り止め大学』ってどこが良いのだろう?
と疑問に感じている方がいるのではないでしょうか。
大学編入は「一般入試」と違って、編入試験を「実施していない大学」があったり、大学によって「実施している学部」「実施していない学部」があったりするため、自分が受験する大学を決めるのが少々難しいですよね。
また、大学編入自体がマイナーな入学制度で、情報を集めることが難しいため、「どこの大学だったら安心して挑戦できるのか分からない」と感じている人も多いはず。
そこで今回は、実際に大学編入を経験し、計5つの大学の編入試験に挑戦したボクが、「大学編入の滑り止め」について解説していきます。
目次
【結論】大学編入の滑り止めを決めるのは難しい
早速結論から述べてしまいますが、大学編入の「滑り止め」を決めるのはけっこう難しいです。
大学編入試験には「一般入試」とは異なる特徴がたくさんあります。
そのため、一般入試の時と同じような感覚で「この大学は滑り止めとして受けてみよう」と決めることができません。
その理由を以降の章で詳しく解説していきます。
大学編入の滑り止めを決めるのが難しい理由
大学編入試験で「滑り止め」として受ける大学を決めるのが難しい理由は、以下の通りです↓
- 大学編入に「偏差値」は関係ないから
- 自分のレベルを「可視化」することが難しいから
- 編入試験を実施しても「合格者0人」となるケースがあるから
大学編入に「偏差値」は関係ないから
一般入試で「滑り止めの大学」を決める際に参考とする情報・数値が「偏差値」ですよね。
みなさんも高校3年生の時に、自分の学力レベルと各大学の「偏差値」を照らし合わせながら、「このくらいの大学だったら自分の実力で”安全圏”に入ることができるな」と考えて「滑り止め」を決定していたのではないでしょうか。
一方で、あなたがこれから挑戦しようとしている大学編入試験は「偏差値」と強い関連性がありません。
つまり、「偏差値」という尺度を用いたところで、大学編入試験における「安全圏」を把握することはできません。
そのため、「大学編入で全落ちは避けたいから、”偏差値が低めの大学”の編入試験も一応受験しておこう」と考えている方は注意して方が良いですよ。
余裕で失敗する可能性があります。
自分のレベルを「可視化」することが難しいから
大学編入試験の「滑り止め」を決めることが難しい理由の一つに、大学編入では「自分のレベルを可視化することが難しい」というものがあります。
一般入試の場合、「全国模試」を利用することで「自分が今どのくらいのレベルにあるのか」「志望校に合格できる確率はどのくらいか」を把握することができますよね。
この「全国模試」の結果によって自分のレベルを「可視化」できるため、「このくらいの大学なら、合格安全圏かな・滑り止めになるかな」といった判断が可能です。
一方で、大学編入ではそもそも「自分のレベル」を把握する手段がありません。
他のライバルと比べた時に、「自分はできる?できない?」を確かめることができないんですよね。
編入試験を実施しても「合格者0人」となるケースがあるから
大学編入では、「編入試験を実施しているのに『合格者が0人』」というケースが時折見られます。
試験を実施しているのに「合格者を出さない」ってチョット怖いですよね。
この大学編入独特の特徴が、「滑り止めの決定」を難しくしています。
一般入試で「滑り止め」として見られるような大学でも、過去の試験情報を確認したところ「前年度の合格者が0人」となっていた場合、その大学を「滑り止め」にする勇気は出ませんよね。
大学編入の滑り止めを決めるのが難しいと実感した体験談
ココでボクの経験談を話しておきます。
ボクが編入受験生だった時、全部で「5校」受験しました。
編入試験に挑戦した大学(偏差値)はそれぞれ、
- 早稲田大学 商学部(71)
- 東北大学 経済学部(63)
- 上智大学 経済学部(68)
- 中央大学 経済学部(66)
- 明治学院大学 経済学部(61)
でした。
(偏差値の数字は『Toshin.com』を参考にしています)
見て分かる通り、通常の一般入試で上記の大学を受験する場合、「滑り止め」となり得るのは「明治学院大学 経済学部」ですよね。
「偏差値」という尺度で見ても、明治学院大学が5校の中で最も低いです。
ただ、ボクが編入試験で最も合格できるか不安だったのは、何を隠そうこの「明治学院大学 経済学部」でした。
実は、「明治学院大学 経済学部」の編入試験は、(ボクの受験年度から数えて)過去3年「合格者0人」だったのです。
過去問を確認してみても「そこまで難しい内容ではない」のに、合格者が1人も出ていない状況だったので、正直合格できる自信がありませんでした。
(結果はなんとか合格することができました)
一般入試で「滑り止め」と判断される(できる)ような大学であっても、大学編入では「滑り止めにできない」ということを覚えておいてください。
「入りやすい大学」を選ぶのが得策
実際に大学編入を経験したボクからすると、志望校を選ぶ際、「滑り止め」という感覚は忘れたほうが良いでしょう。
「できるだけ失敗したくない」と思っている方は、「入りやすい大学」を選ぶのが得策と言えます。
大学編入で「滑り止め」の候補となるような大学を探すのは難しいですが、「入りやすい大学」を判断することは可能です。
「入りやすい大学」を判断する基準は以下の通りです↓
- 受験科目数が少ない
- 面接試験が無い
- 【文転の受験生】数学がある
- 合格者数が比較的多い
- TOEIC・英検などの提出が無い / 指定のスコアが低い
上記の基準を照らし合わせると、「中央大学 経済学部」や「東北大学 経済学部」は入りやすい大学と判断することができるんです。
そうです。
一般入試の時には「難しい大学」と言われるような大学でも、大学編入では「入りやすい大学」になり得ます。
入りやすい大学に関しては「読むだけでチャンスが増える!編入しやすい大学とは?」という記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。
「大学編入の滑り止め」まとめ
今回は、「大学編入の滑り止め」に関して、大学編入経験者の視点を交えて解説してきました。
編入試験の全落ちを避けるために「滑り止め」の大学を探そうとしていた方がいるかもしれませんが、大学編入では基本的に「滑り止め」の大学を決めることができないことを認識しておいてください。
そのため、大学編入において「入りやすい大学」を探してみることをおススメします。
また、「大学編入で全落ちを避けるための具体的な戦略【やるべきことは3つ】」という記事に、全落ちを避けるための戦略について解説しています。
コチラの記事を参考に、「全落ちを避けるための行動」を意識してみてください!