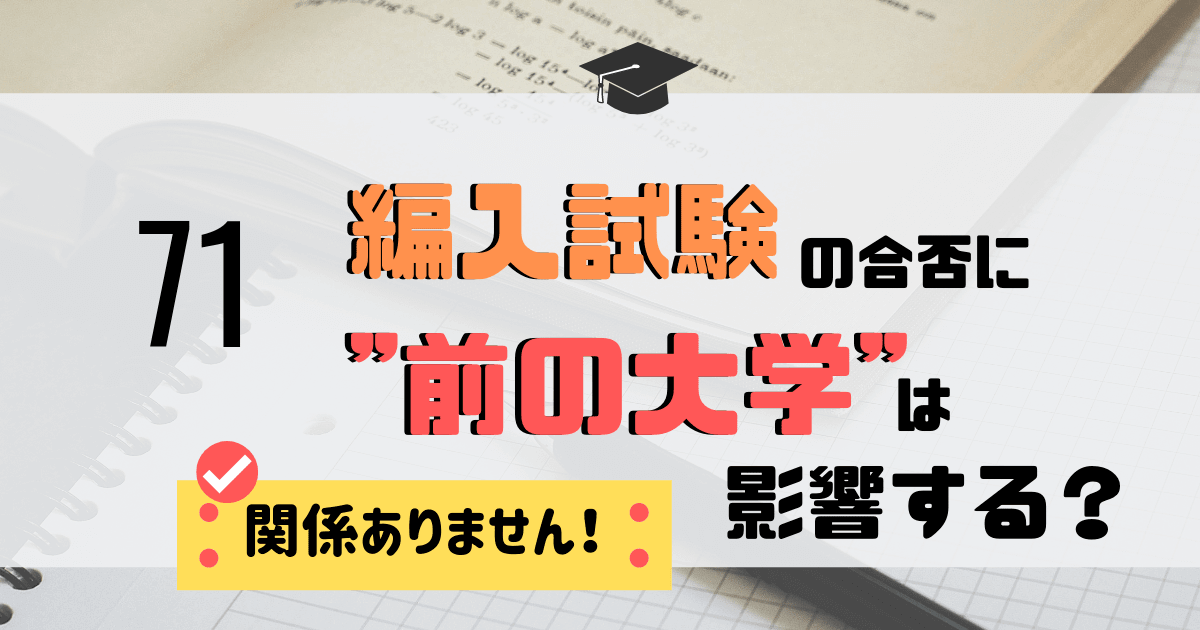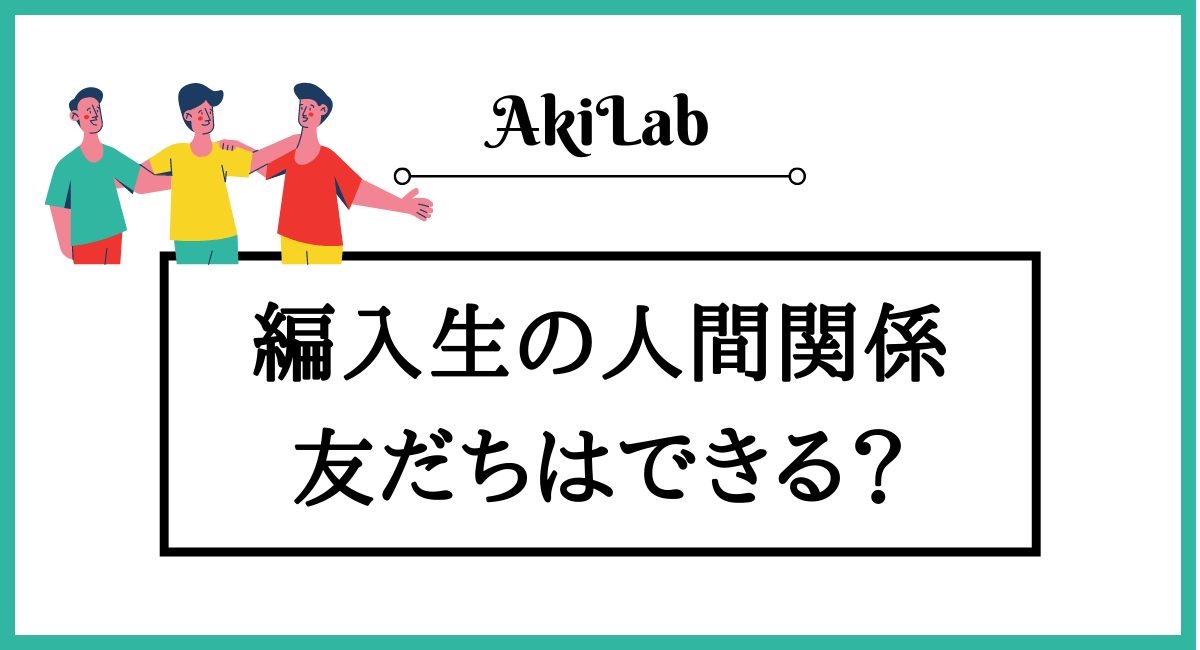大学編入試験の全落ちを避けたい!
具体的戦略を解説します。
どうも、編入試験で合格・不合格のどちらも経験していますアキラです。
ボクは専門学校時代に「大学編入」に挑戦し、早稲田大学・東北大学・中央大学・明治学院大学の4つの大学に同時合格することができました。
そして、専門学校から「早稲田大学商学部」へステップアップすることに成功しました。
一方で、ボクの受験校は全部で5校。
1校だけ「編入試験不合格」も経験しています。
ボクの不合格体験談ついては「不合格を経験した話」で詳細に話しているので、気になる方はチェックしてみてください。
そんな大学編入の”酸いも甘いも”経験しているボクが、「大学編入で全落ちを避けるための戦略」について解説していきます。
現在、自分をステップアップさせることを目的に「大学編入」を目指している方の中に、「編入試験で全落ちしてしまったらどうしよう」と不安に感じている方もいるはず。
何としてでも「全落ち」だけは避けたいという方は、ぜひ当記事を参考に日々の勉強に取り組んでみてください。
目次
大学編入で全落ちするとどうなる?
大学編入試験の「志望校全て」で不合格になってしまうと、厳しい現実に直面する可能性があります。
特に、現在「専門学校」や「短大」などに通いながら大学編入を目指している方は、大学編入で「全落ち」した後の進路先が無いため、厳しい状況に陥ります。
大学編入は、通常「3年次編入」となっています。
つまり、3年生になる年に、新しい大学へ転校するイメージです。
専門学校や短大に通っている編入受験生は、「2年生」の秋~冬にかけて編入試験を受験することになります。
通常の専門学生・短大生であれば、2年生は「就職活動」をするタイミングですよね。
一方で、編入受験生の場合は、大学編入の勉強をしながら「就職活動」も進めることは難しいです。
その結果、万が一編入試験で「全落ち」してしまうと、進学先・就職先が決まっていない状態で専門学校・短大を卒業しなければいけないという最悪のケースに直面します。
こんなことが起こり得るので、何としてでも「全落ち」は避けたいところですよね。
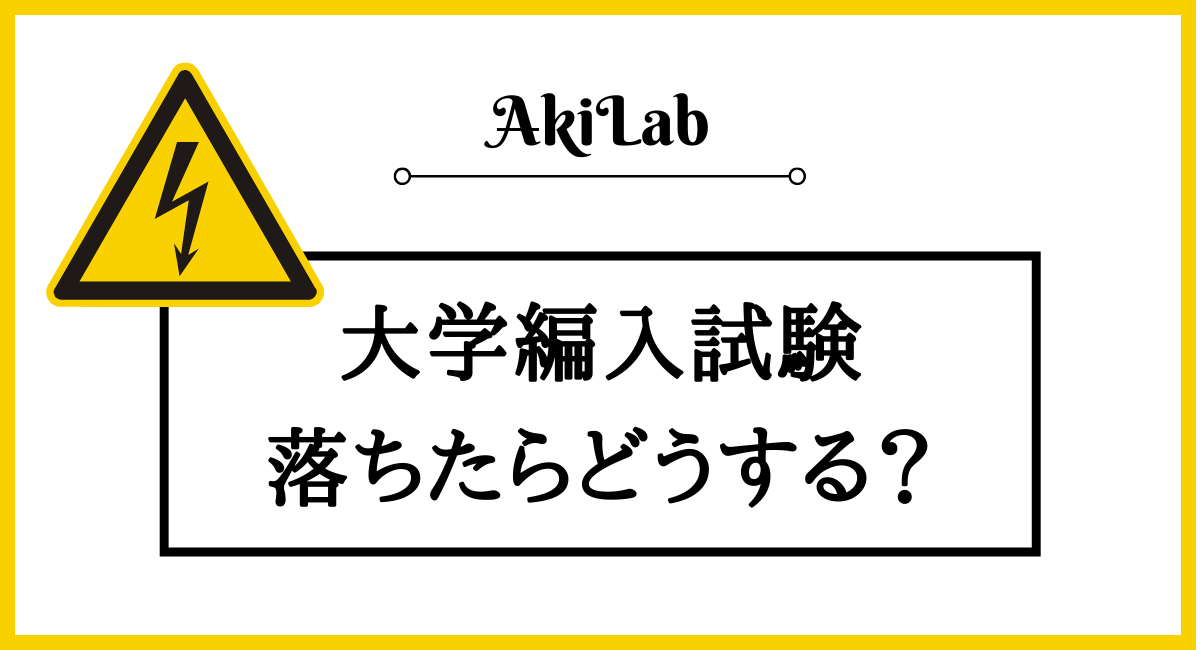 大学編入試験に落ちたらどうなる?その後の選択肢も解説
大学編入試験に落ちたらどうなる?その後の選択肢も解説
大学編入で全落ちを避けるための戦略【3つ】
ボクは大学編入の合格・不合格の両方を経験しているため、
- 合格するためには「何が必要か」
- 不合格を避けるためには「何が必要か」
をそれなりに把握できている自信があります。
ここからは、そんなボクが考える「大学編入で全落ちを避けるための具体的な戦略」について解説していきます。
といっても、そこまで複雑な戦略ではありません。
以下で説明する戦略を意識して勉強を進めてもらえれば、「全落ち」という最悪なシナリオは避けることができます。
- TOEICスコアを「600点」以上取得する
- 「専門科目の基礎知識」を一通り理解する
- 「入りやすい大学」を受験する
TOEICスコアを「600点」以上取得する
一つ目の戦略は「TOEICスコアを600点以上取得する」というものです。
大学編入の合否に大きな影響を及ぼすものの一つに「TOEICスコア」があります。
TOEICの点数を伸ばす勉強をサボってしまうと、編入試験で合格できる可能性が低くなってしまいます。
そのため、「全落ち」を避けたいなら、ある程度TOEICスコアを伸ばしておく必要があります。
これはボクの経験から推測している数字でしかありませんが、全落ちを避けるためには、TOEICスコアを「600点以上」にしておきたいところです。
TOEICスコアが600点程度あれば、中級レベルの大学なら「足切り(出願資格)を突破」できますし、それなりの評価はしてもらえるはずです。
また、「英語が苦手」「TOEICスコアがもともとかなり低い(300点以下)」という方でも、「正しい勉強」を毎日コツコツ積めば、TOEIC600点は取得できます。
勉強に自信が無い方でも、「TOEIC600点」という目標は十分達成できるものでしょう。
編入試験の「全落ち」だけは避けたいなら、TOEICの勉強を継続して行うことを意識してみてください。
「専門科目の基礎知識」を一通り理解する
TOEICと並んで、大学編入試験に欠かせないのが「専門科目」です。
「専門科目」とは、あなたが目指している学部・学科に関連する科目のことです。
経済学部なら「経済学」、法学部なら「法学」、社会学部なら「社会学」が専門科目と呼ばれるものですね。
編入試験を実施している大学・学部のほとんどが、何かしらの形式で「専門科目の知識がどのくらいあるか」を試してきます。
そのため、「専門科目」の勉強をサボってしまったら、確実に「全落ち」が待っています。
「何としても全落ちだけは避けたい」という方は、専門科目の勉強をする際に、「基礎部分だけはとりあえず理解しよう」という意識で勉強に取り組んでみてください。
多くの人が勘違いしているポイントでもありますが、編入試験の専門科目の問題は「基礎知識」の範囲から出題されるケースが多いです。
その理由は、編入試験で求められているのが「大学1・2年次に学習する専門科目のレベル」だからです。
このことから、とりあえず「専門科目の基礎知識」だけは理解している状態に持っていくことができれば、「編入試験で全落ちする確率は減らせる」と考えることができます。
ちなみに、「基礎を理解する」ことが最優先事項であるため、「難しい参考書・分厚い参考書」を使う必要はありません。
内容が端的にまとまっていて読みやすい参考書を使って、毎日勉強を継続できる環境を整える・モチベーションを維持することが大切です。
「入りやすい大学」を受験する
大学編入の全落ちを避けるための戦略として、「入りやすい大学を受験する」というものも紹介しておきます。
これを聞いて、「大学編入に入りやすい大学なんてあるの?」と不思議に思った方もいるかもしれません。
少なくとも、実際に大学編入を経験したボクからすると、編入試験で合格しやすい・大学編入で入りやすい大学は「あります」。
一定の基準を満たしている大学は、合格チャンスが広いため、「全落ち」リスクの抑制につながります。
その基準とは以下の5つです。
- 勉強すべき科目数が少ない
- 面接試験がない
- 数学がある
- 毎年一定数の合格者がでる
- TOEICなどの提出が必要ない
詳しくは「入りやすい大学ってあるの?【穴場アリ】」という記事を参考にしていただきたいのですが、上記に挙げた基準を満たしている大学があれば、それは「入りやすい大学」と言うことができます。
ちなみに「すべての基準」を満たしている必要はありません。
上記の基準のうち、2・3個満たしている大学は入りやすい大学と捉えて良いでしょう。
そして、入りやすい大学を志望校の一つとすることで、編入試験ですべて不合格になる可能性を下げることが可能となります。
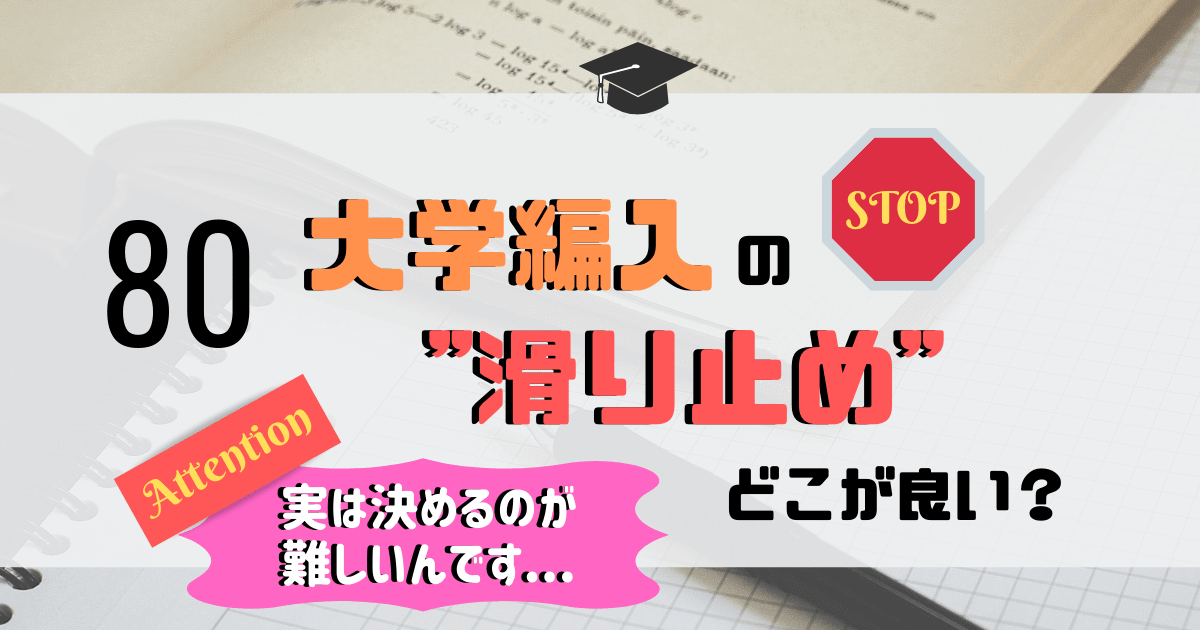 大学編入試験の「滑り止め」はどこが良い?【経験者談】
大学編入試験の「滑り止め」はどこが良い?【経験者談】
大学編入で全落ちする人は「やるべきこと」をやっていないだけ
上記で紹介した戦略を実行することで、確実に「全落ち」のリスクを抑制することが可能です。
思いもよらない「編入試験の全落ち」によって、進路先・就職先が無いまま卒業しなくてはいけない状況を避けたい方は、ぜひ意識してみてください。
ちなみに、大学編入で「全落ち」してしまう人は、単純に「自分がやるべきこと」をやっていないだけの可能性が高いです。
「勉強が苦手」「英語が思うように成長しない」という人でも、毎日継続して「やるべきこと」をこなしていれば、「3校中1校に合格」「すべり止め目的で受験した大学に合格」することができ、全落ちという最悪のシナリオは避けることができます。
全力で「TOEIC対策」「専門科目の勉強」をしている人が、受験校すべての編入試験に落ちてしまうということは非常に考えにくいです。
一方、「TOEIC対策をしない・専門科目の勉強をサボる」ような人は、もちろんどこにも合格できません。
ものすごく当たり前のことを言えば、
- 勉強している人…「全落ち」はない
- 勉強していない人…「全落ち」の可能性大
ということです。
当記事をご覧になっているあなたは、「記念受験組」とならないように、限られた時間を有効活用して、少しずつ勉強を進めていってください!
「大学編入で全落ちを避けるための戦略」まとめ
今回は、「大学編入で全落ちを避けるための戦略」について解説してきました。
大学編入は情報が少なく、未知の部分も多くある入試制度であるため、「全落ちを避けるためにはどうすれば良いのだろう」と不安に感じていた方も多いのではないでしょうか?
大学編入における「最悪のシナリオ」を避けるためにも、ぜひ当エントリーの内容を参考に、毎日の勉強に取り組んでください。
ちなみに、当記事で紹介した戦略は、あくまでも「全落ちを避けるため」のものであり、「ハイレベルな大学に編入したい」「旧帝大・MARCHに編入学したい」と考えている方向けの内容ではありません。
「自分をもっと成長させるために大学編入に挑むんだ」という強い意識を持った編入受験生は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください↓